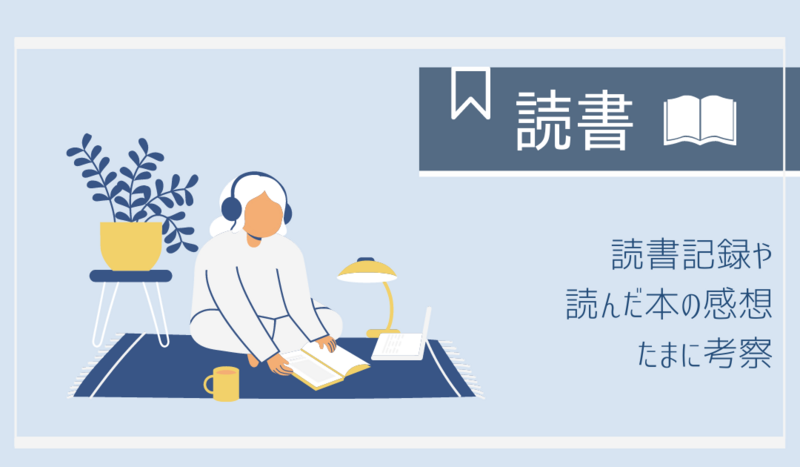①マーロウにはもっと率直に喋って欲しい。コンラッド「闇の奥」を読んだ

「闇の奥」はこんな話
時代背景
時は19世紀末。帝国主義の時代。欧州列強による植民地化が進み、未開の地であったアフリカ大陸の色は次々と塗り替えられていた。
アフリカの植民地支配といえば思い出すのはこの人。歴史の教科書等でお目にかかったことがあると思う。「地球をの表面を1インチといえども多く取らなければならない」などと発言し、植民地政策を推し進めたイギリス人。

by Edward Linley Sambourne
Wikipediaによると、著書でこのように述べている。
神は世界地図がより多くイギリス領に塗られることを望んでおられる。できることなら私は夜空に浮かぶ星さえも併合したい。
陸じゃ飽き足らず空にまで支配を広げたいと願うセシル・ローズ。しかも神のご意思だと思ってらっしゃる。
今生きてたら絶対に宇宙植民地化計画とかゴリ押ししてそうだ。
イギリスカラーに染まっていく火星の地図を眺めつつ、バカラグラスに注いだウイスキー片手にご満悦。次の星に狙いを定めるセシル・ローズ。
ちなみに本とセシル・ローズは一切関係がない。
予備知識はバッチリ(??) ということで、次。
あらすじ・著者情報
場所はイギリスのテムズ川。夕暮れに浮かぶ船の上で物語がスタート。船員の1人、マーロウが唐突に語り始める。それを別の乗組員が聞いているというスタイルで、語りが2重構造になっている。マーロウが内側。聞き手の船員が外側。
マーロウによる語りが9割くらいなので、聞き手である船員(Xとします)の影は非常に薄いです。あと一歩で透明人間になるほど。
マーロウの回想は、当時ベルギーの支配下にあったコンゴに向かう船旅の過程、その途中に聞いた「クルツ」という謎の人物、クルツがいる出張所に辿り着いてからの出来事、の3つくらいがメイン。
コンゴ川を遡行しながら、未開の地の奥へ奥へと分け入っていく。ジャングルが深くなり、文明の影は薄れ、ただそこに存在する自然に生命を脅かされる世界がゆっくりと近づいてくる。
その河を遡ることは、草木が繁茂し、巨木が王者であった世界の始まりへと戻っていく旅だった。空虚な河の流れ、ものすごい沈黙、見通せない森。大気は生ぬるく厚く、重苦しく、よどんでいた。太陽の輝きには喜びなど全くなかった。
そしてこの生命の沈黙は、平和とは似ても似つかないものだった。それは測りしれない意図を持った無情な力の沈黙だった。それは復讐心に満ちた顔つきで人間を見ていた。
コンラッド自身の、1890年のコンゴでの体験に基づいています。1857年にポーランドの没落貴族として生まれており、紆余曲折を経て1886年頃にイギリス国籍を取得。Wikipediaで読みましたが、波乱万丈な人生。「闇の奥」より彼の人生遍歴を本にした方が面白そう(失礼極まりない)。
ポストコロニアル批評と感想
詳細は省きますが、「闇の奥」は植民地支配の実態を批判的な視点で描いたものなのかということに関する議論は様々です。
- 植民地支配を否定的に描写してはいるが不十分
- そもそも植民地支配の糾弾を目的とした小説ではない
等の意見があるよう。著者をレイシストとする批評もある。
現代人の感覚からすれば、黒人を労働奴隷として扱う非人道的行為への非難は十分といえない。著者自身、作中で”savege(野蛮人)”、”nigger(黒人の蔑称)”を用いているそうです。日本語では「黒んぼ」「未開人」などの言葉が何度も出てきました。
それでも、全体として植民地支配を「是」としていないことはよく伝わってきます。帝国主義が推し進められ、大英帝国万歳の空気感のなかでこの小説を書いたことに大きな価値があると感じます。
「(略)こんな風に感じる者は誰もいないだろう。僕たちを救っているものは、効率――効率に専念することにあるんだ。だがこうした連中は、本当に大した連中ではなかった。彼らは植民者では全くなかった。彼らの支配は単なる搾取で、それ以上のものではなかったと僕は思う。彼らは征服者だったから、そのためには暴力さえあればいいんだ――(略)
地上の征服は僕たちと肌の色のちがう人達や、ちょっと鼻の低い人達から奪い取ることなんだが、よく考えればきれいごとじゃない。それを償うのは理念だけだ。(略)」
これはごく最初の方に出てくるマーロウのセリフです。
まず初めに思ったのが「植民」という言葉の定義。「植」という漢字からして、そこには何か豊かにするような意味があるはずなのに、完全に植民地=征服=悪の図式が出来上がっていた。
【植民】
本国以外の土地に移住・定着して経済的に開発すること。また、その移住民。
そうだよね!元々はこういう意味なんだよね!という感じ。現代でいうODAとか青年海外協力隊的が近いかな、と。定住するわけじゃないので正確には違うけど。
彼らは植民者では全くなかった
というマーロウの言葉に+1000ポイント。
植民者=征服者ではないけれど、その後の歴史によって植民地は搾取・支配の構造ができるだけなので悪、ということが判明し、結果的に植民地=支配=悪という図式になってたんだよね、と。なんというか、当たり前のことを再発見した時の気持ち。
発展途上国開発を支援する先進国として使命感を持って開拓に取り組んでいる場合は「世界をよりよくしている」のでOK。というのが語り手マーロウの感覚なのかもしれない。ただ現代ほど倫理観が発達していないので、あくまで彼らが「未開人」ということに変わりわない。
未開人である君たちを、我々文明人が導いてあげよう。そしてそれは君たちにとっても良いことなのだ。的な感覚は、著者自身もどこかに持っていたんだと思う。けれど実態を見た限りでは、ただの搾取じゃないか、と。
まあ全部私の妄想ですが。
(※船長としての仕事を見つけてくれた叔母が「あの無知な多くの人々をひどい生活状態から救い出す」と発言した時には酷く居心地が悪くなり、「会社は利益の為に経営されているんですよ」と仄めかしたといった描写があるので、直前の私の妄想は的外れの可能性が高い)
利益を追求した結果、そこに住む人々の暮らしが向上するのはOKってスタンスなんでしょうか。うーむ分からぬ。まだまだ理解が浅いので。
なんというか、マーロウは一筋縄ではいかない。そこがいいんだけど。先程引用したマーロウのセリフは回想が始まる前なので、かなり率直に植民地支配に関して意見を言ってくれたと思う。だけど回想が始まるとこうはいかない。
彼にとって挿話の意味は、月の幽霊のような光によってうすぼんやりとした暈輪(かさ)のひとつが時に見えるように、陽の光が輝いた時だけ霞が見えるように、話の内側ではなく、話を包み込んでいる外側にあるのだった。
これは外側の語り手(船員X)の言葉。
なので、これ以降マーロウの語りは不透明度が高くなる。遠回しなあまり何言ってるか分からないこともしばしば。褒めてるのか皮肉なのか、そのまま受け取ればいいのか裏の意味があるのか。
サリンジャー先生は鍵さえあれば解ける暗号、という気がしないでもなかったけど、コンラッド先生はそもそも鍵とか用意されてない感じがします。
オブラートどころか餃子の皮に包まれてる。もっと分厚いかも。でも船員Xのいうことを信じるのであれば、話の内側ではなくそれを包み込んでいる外側に意味があるらしいので、一縷の望みはある。きっと。
そんなことが言いたくて感想を書き始めたものの、辿り着かないまま終わりを迎えました。なのでタイトルに①を追加。たぶん次回に続きます。
ひとこと
感想をまともに述べられるようになるには相当な訓練が必要です。読書感想文とか大嫌いでした(笑)
ありがとうございました。